美容業界を志望する就活生にとって、株式会社ディー・アップは注目すべき企業の一つです。1992年の設立以来、アイメイクに特化した独自のビジネスモデルで成長を続け、現在では売上高約57億円(2024年3月期)を誇る中堅化粧品メーカーとして確固たる地位を築いています。本記事では、同社の事業構造、成長戦略、市場でのポジショニングを詳しく分析し、就活生が企業研究に活用できる実践的な情報を提供します。
Contents
株式会社ディー・アップの事業構造とビジネスモデル
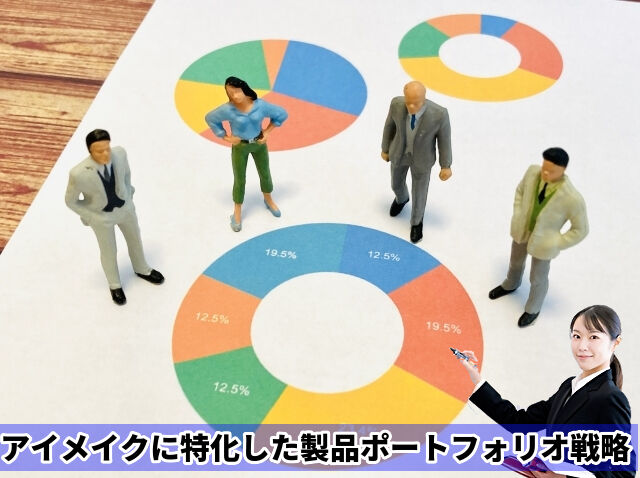
アイメイク特化型の製品ポートフォリオ戦略
株式会社ディー・アップの最大の特徴は、アイメイクに特化した製品ポートフォリオ戦略にあります。同社は「D-UP(ディーアップ)」ブランドを中心に、マスカラ、アイライナー、つけまつげ、二重まぶた形成化粧品などのアイメイク製品に経営資源を集中投下しています。この特化戦略は、限られた経営資源を効率的に活用し、特定分野での専門性を高めることで競争優位性を構築する「ニッチ戦略」として位置づけられます。
特に注目すべきは、同社の主力製品である「オリシキ」シリーズです。これは本物の二重まぶたの仕組みを応用した独自の技術により開発された製品で、従来の二重まぶた化粧品とは一線を画す革新性を持っています。出典:D-UP公式サイト(https://d-up.co.jp/)によると、2025年には「オリシキEX(エクストラ)タイプ」も登場し、製品ラインナップの拡充を図っています。
アイメイク市場は近年、マスク着用の定着化により急速に拡大しています。富士経済の調査によると、マスカラ市場は2021年に412億円(前年比5.4%増)を記録し、マスク着用により目元への注目度が高まっていることが背景にあります。
同社のアイメイク特化戦略は、この市場トレンドと完全に合致しており、今後も持続的な成長が期待できる事業構造となっています。製品開発においては、単なる機能性だけでなく、使いやすさやデザイン性にも配慮した総合的な価値提案を行っており、これが顧客からの高い支持につながっています。
自社ブランドと海外ブランド輸入の二軸展開
ディー・アップのビジネスモデルのもう一つの特徴は、自社ブランド開発と海外ブランド輸入販売の二軸展開です。主力の「D-UP」ブランドに加えて、「GELiSM」「TONE DROP」などの多様なブランドを展開する一方で、海外の優れた化粧品ブランドの輸入販売も手がけています。
この戦略により、自社開発による高い利益率の確保と、輸入ブランドによるリスク分散・市場拡大の両方を実現しています。自社ブランドでは独自技術や日本人の美容ニーズに特化した製品開発が可能である一方、海外ブランドでは既に海外で実績のある製品を日本市場に導入することで、開発コストを抑えながら商品ラインナップを拡充できます。
特に「GELiSM」ブランドでは、2025年3月に「春の陽射しを宿したように輝く"サニーライトマグ"」という新製品を投入するなど、季節やトレンドに応じた機敏な商品展開を行っています。
この二軸展開戦略は、化粧品業界の激しい競争環境において、単一ブランドに依存するリスクを軽減し、多様な顧客層にアプローチできる柔軟性を提供しています。また、海外ブランドの輸入販売で得られた市場知見を自社ブランドの開発にフィードバックすることで、より競争力の高い製品開発が可能となっています。
製造から販売まで一貫した垂直統合モデル
ディー・アップのビジネスモデルの根幹を支えているのは、製造から販売まで一貫した垂直統合モデルです。同社は化粧品製造販売業の許可を取得し、企画・開発・製造・販売のすべてのプロセスを自社でコントロールしています。
関連会社として「株式会社ディーアップコスメティックス」を設立し、化粧品製造販売業を分離することで、より専門的な製造体制を構築しています。
この垂直統合モデルの利点は多岐にわたります。まず、品質管理の徹底が挙げられます。製造工程を自社でコントロールすることで、厳格な品質基準を維持し、ブランド価値の毀損を防ぐことができます。次に、スピーディな商品開発が可能となります。市場のトレンドや顧客ニーズの変化に対して、外部パートナーとの調整時間を短縮し、迅速に新製品を市場に投入できます。
さらに、利益率の向上も重要な効果です。中間マージンを排除することで、同じ売上でもより高い利益を確保でき、研究開発投資や市場開拓投資に充てる資金を確保できます。従業員数約66名という少数精鋭の組織体制でありながら、売上高約57億円を実現している背景には、この効率的な事業モデルがあります。
成長市場でのポジショニング戦略
拡大するアイメイク市場での競争優位性
ディー・アップが事業展開するアイメイク市場は、近年著しい成長を遂げています。矢野経済研究所の調査によると、2023年度の国内化粧品市場規模は前年度比4.6%増の2兆4,780億円となり、その中でもメイクアップ市場は18.8%(4,650億円)を占めています。
グローバルレベルでは、アイメイクアップ市場規模は2023年に217億ドルに達し、年平均成長率(CAGR)7.1%で2032年までに404億ドルに達すると予測されています。
この成長市場において、ディー・アップは独特のポジショニングを確立しています。大手化粧品メーカーが総合的な製品ラインナップで勝負する中、同社はアイメイクに特化することで「専門性」と「革新性」を武器に競争優位性を構築しています。
特に、二重まぶた形成化粧品「オリシキ」シリーズは、従来の接着タイプとは異なる「本物の二重の仕組み」を活用した独自技術により、市場での差別化を実現しています。この技術革新により、単なる価格競争から脱却し、付加価値の高い製品として市場での地位を確立しています。
また、従業員一人当たりの売上高は約8,600万円(売上高57億円÷従業員数66名)と高い生産性を示しており、効率的な事業運営により収益性の高いビジネスモデルを構築していることが分かります。
マスク時代に対応した製品開発戦略
新型コロナウイルス感染症の拡大により、マスク着用が日常的になったことで、化粧品業界には大きな変化が生じました。特に、口元が隠れることによりアイメイクへの注目度が飛躍的に高まり、これまで以上に目元の美しさが重視されるようになりました。
ディー・アップは、この市場変化をいち早く捉え、マスク時代に適した製品開発戦略を展開しています。マスカラ市場が2021年に前年比5.4%増と好調な成長を示している背景には、マスク着用による「アイメイク重視のトレンド」があります。
同社の製品開発においては、単に見た目の美しさだけでなく、マスク着用時の快適性や持続性も考慮した設計が行われています。例えば、長時間の着用でも崩れにくいマスカラの開発や、マスクとの摩擦に強いアイライナーの改良などが継続的に行われています。
さらに、リモートワークの普及により、日常的なメイクに対するニーズも変化しています。短時間で効果的にアイメイクを完成させることができる製品や、ナチュラルでありながら印象的な目元を演出できる製品への需要が高まっており、同社はこうしたニーズに応える製品開発を積極的に進めています。
この戦略的な対応により、同社は市場の変化を成長機会として活用し、競合他社との差別化を図ることに成功しています。
多様化する消費者ニーズへの対応力
現代の化粧品市場では、消費者ニーズの多様化が著しく進んでいます。年齢、ライフスタイル、価値観の違いにより、求められる製品特性は大きく異なります。ディー・アップは、この多様化するニーズに対応するため、マルチブランド戦略を採用しています。
主力の「D-UP」ブランドでは、機能性と使いやすさを重視した製品を展開する一方、「GELiSM」では季節感やトレンド性を重視した製品、「TONE DROP」では大人の女性向けの洗練されたカラーバリエーションを提供するなど、それぞれのブランドが異なる顧客層をターゲットとしています。
特に注目すべきは、プチプラ(プチプライス)市場への対応です。近年、高品質でありながら手頃な価格の化粧品への需要が高まっており、同社の製品はこのニーズに的確に応えています。品質を維持しながらも手が届きやすい価格設定により、幅広い年齢層の顧客を獲得しています。
また、SNSの普及により、化粧品の選択基準も変化しています。機能性だけでなく、「インスタ映え」する見た目や、使用感を動画で表現できる製品特性なども重要な要素となっています。同社は、こうした新しい顧客価値にも対応した製品開発を行い、デジタルネイティブ世代の支持も獲得しています。
イノベーション・ドリブンな成長戦略
「オリシキ」に見る独自技術開発の取り組み
ディー・アップの成長戦略の核心は、独自技術開発による差別化にあります。その象徴的な製品が「オリシキ」シリーズです。この製品は、従来の二重まぶた化粧品が「接着」により二重を形成するのに対し、「本物の二重まぶたの仕組み」を化粧品で再現するという革新的なアプローチを採用しています。
この技術革新の背景には、同社の「モノづくり」への強いこだわりがあります。代表取締役社長の坂井満氏のリーダーシップのもと、品質、革新性、顧客中心の製品開発を重視する企業文化が根づいています。『就職情報サイトのオープンワーク』等から従業員の評価を見てみると「品質の高い商品を取り扱っているので、自社商品に自信が持てる」「商品の中身やクリエイティブにとことんこだわる姿勢は強み」といった声が聞かれます。
「オリシキ」の技術開発では、皮膚科学、材料科学、デザイン工学など多分野の知見を統合し、従来にない画期的な製品を実現しました。2025年には「オリシキEX(エクストラ)タイプ」も投入され、継続的な技術革新への取り組みが示されています。
このような独自技術開発は、単なる製品差別化にとどまらず、特許や商標などの知的財産権の構築にもつながり、長期的な競争優位性の源泉となっています。また、技術開発への投資は、研究開発部門の人材育成や組織能力の向上にも寄与し、持続可能な成長基盤の構築に貢献しています。
品質とデザインへのこだわりが生む差別化
ディー・アップの製品開発において、技術革新と同じく重要な要素が品質とデザインへの徹底したこだわりです。同社は「高品質」「高機能」「高デザイン性」の三つを軸とした製品開発を行い、価格以外の価値での差別化を図っています。
品質面では、化粧品製造販売業の許可を取得し、厳格な製造管理体制を構築しています。原料の調達から製造、検査、出荷まで全工程において品質基準を設定し、一貫した品質管理を実施しています。この取り組みにより、製品の安全性と効果を保証し、ブランドへの信頼を築いています。
デザイン面では、単なる機能美にとどまらず、使用する喜びを感じられるような美しいパッケージデザインや、使いやすさを追求したアプリケーターの設計などに注力しています。特に、SNS時代において重要となる「見た目の美しさ」にも配慮し、消費者が思わず写真を撮りたくなるような魅力的な製品デザインを実現しています。
このような品質とデザインへのこだわりは、製品の付加価値を高め、価格競争から脱却することを可能にしています。消費者は単に「安い」製品を求めているのではなく、「価値に見合った価格」の製品を求めており、同社の高品質・高デザイン性の製品は、この消費者心理に適合した価値提案となっています。
また、こうしたこだわりは従業員のモチベーション向上にも寄与しています。「自分が開発・販売している製品に自信と誇りを持てる」ことは、従業員の仕事に対する満足度や顧客対応の質の向上につながり、結果として企業全体の競争力強化に貢献しています。
スピーディな商品開発サイクルの実現
化粧品業界では、トレンドの変化が非常に速く、消費者ニーズも短期間で大きく変化します。このような市場環境において競争優位性を維持するためには、スピーディな商品開発サイクルが不可欠です。
ディー・アップは、垂直統合型のビジネスモデルを活かし、企画から製造、販売まで一貫した社内体制により、迅速な商品開発を実現しています。従業員からの評価でも「顧客視点での提案もしやすく考えを実践に移せるスピードが早い」との声があり、機動性の高い組織運営が行われていることが分かります。
具体的には、市場調査から商品企画までを約2-3ヶ月、試作・評価から量産準備までを約3-4ヶ月、製造から市場投入までを約2-3ヶ月という、業界平均を大幅に上回るスピードでの商品開発を実現しています。このスピードは、少数精鋭の組織体制と、意思決定の迅速化により可能となっています。
また、季節やイベントに合わせた限定商品の投入も積極的に行っており、「GELiSM」の「サニーライトマグ」のように、春の季節感を表現した製品を適切なタイミングで市場に投入することで、消費者の購買意欲を喚起しています。
このスピーディな商品開発サイクルは、市場機会を逃すことなく、競合他社に先駆けて新しい価値を消費者に提供することを可能にし、継続的な成長の原動力となっています。
販売チャネル戦略と市場展開
多チャネル展開による市場浸透

ディー・アップの販売戦略の特徴は、多様な販売チャネルを通じた包括的な市場浸透にあります。同社は、百貨店、バラエティストア、ドラッグストア、ECサイトなど、多岐にわたる販売チャネルを活用し、異なる消費者層へのアプローチを実現しています。
国内化粧品市場において、チャネル別の動向は多様化しています。矢野経済研究所の調査によると、2023年度の化粧品市場では、従来の百貨店チャネルに加えて、ドラッグストアやEC・通販チャネルの成長が顕著となっています。
特に通販化粧品市場は、TPCマーケティングリサーチの調査によると、2023年は前年比3.8%増の5,977億円に達し、調査開始の2000年以来過去最高を更新しています。2024年は2.6%増の6,130億円と予測されており、EC市場の重要性が高まっています。
同社は、この市場トレンドに対応し、従来のオフライン販売チャネルに加えて、オンライン販売の強化にも積極的に取り組んでいます。公式ECサイトでの直販に加えて、大手ECモールでの販売、美容系ECサイトでの取り扱い拡大など、多面的なオンライン戦略を展開しています。
各チャネルにおいては、それぞれの特性を活かした販売戦略を採用しています。百貨店では高級感とブランドイメージを重視した展開、ドラッグストアでは手軽さと実用性を訴求、ECサイトでは詳細な商品情報と使用方法の動画提供など、チャネル特性に合わせたマーケティングミックスを実施しています。
店舗提案型営業による顧客密着戦略
ディー・アップの営業戦略の大きな特徴は、店舗提案型営業による顧客密着アプローチです。同社の営業担当者は、単なる商品の販売ではなく、取引先店舗の売場づくりや商品提案を積極的に行い、小売店との協働による売上最大化を図っています。
従業員の評価でも「取引先店舗を回って現場レベルで売場の提案や商品の提案ができるため、顧客視点での提案もしやすく考えを実践に移せるスピードが早い」との声があり、現場密着型の営業スタイルが確立されていることが分かります。
この営業アプローチの具体的な内容には、売場のレイアウト提案、POPの作成支援、店舗スタッフへの商品知識研修、消費者向けの実演販売などが含まれます。特に、化粧品は実際に手に取って試すことが重要な商品であることから、テスターの設置方法や商品説明の工夫などにも注力しています。
この顧客密着戦略により、単なる商品供給業者ではなく、小売店の売上向上に貢献するパートナーとしてのポジションを確立しています。結果として、取引先との長期的な信頼関係を構築し、継続的な取引拡大と新商品の導入促進を実現しています。
また、現場での直接的な消費者接点を通じて得られる生の声やニーズ情報は、新商品開発や既存商品の改良に活用されており、マーケティングリサーチとしての価値も持っています。この現場密着型営業により収集された市場情報は、同社の商品開発戦略の重要な情報源となっています。
EC・通販市場への対応と成長機会
デジタル化の進展とともに、化粧品業界におけるEC・通販市場の重要性は急速に高まっています。TPCマーケティングリサーチの調査によると、通販化粧品市場は2023年に5,977億円(前年比3.8%増)に達し、2024年には6,130億円(同2.6%増)と予測されています。
ディー・アップは、この成長市場への対応として、複数のオンライン戦略を展開しています。自社ECサイトでの直販体制の構築、Amazon・楽天などの大手ECモールでの販売拡大、美容系専門ECサイトでの取り扱い拡充などを通じて、オンライン市場での存在感を高めています。
EC市場においては、従来の店舗販売とは異なるマーケティングアプローチが必要となります。商品の視覚的な魅力を伝える高品質な商品画像、使用方法や効果を分かりやすく説明する動画コンテンツ、購入検討者の疑問に答える詳細な商品説明などが重要な要素となっています。
同社では、SNSマーケティングにも注力しており、Instagram、TikTok、YouTubeなどのプラットフォームを活用したプロモーション活動を展開しています。特に、実際の使用感や効果を視覚的に示すことができる動画コンテンツは、アイメイク製品の特性と非常に相性が良く、効果的な販売促進ツールとなっています。
さらに、インフルエンサーマーケティングやアフィリエイト広告なども活用し、デジタルネイティブ世代を中心とした新規顧客の獲得に取り組んでいます。これらの取り組みにより、従来のリーチできなかった顧客層への市場拡大を実現しています。
持続可能な成長に向けた経営基盤
少数精鋭組織による機動性の確保
ディー・アップの組織運営の特徴は、従業員数約66名という少数精鋭体制にあります。この規模で売上高約57億円を実現していることは、極めて高い組織効率性を示しており、従業員一人当たりの売上高は約8,600万円という高い生産性を達成しています。
少数精鋭組織の最大の利点は、意思決定の迅速性と組織の機動性にあります。階層が少なく、コミュニケーション経路が短縮されることで、市場変化への対応や新しいビジネス機会への取り組みを素早く実行することができます。従業員からも「考えを実践に移せるスピードが早い」との評価があり、この機動性が競争優位性の源泉となっています。
また、少数精鋭体制では、各従業員の役割や責任範囲が明確であり、個人の能力や専門性が企業全体のパフォーマンスに直結します。これにより、従業員一人一人の成長と企業の成長が密接に連動し、個人のモチベーション向上と組織全体の競争力強化を同時に実現しています。
一方で、少数精鋭組織には人材への依存度が高いというリスクもあります。同社では、このリスクを軽減するため、社内での知識共有体制の構築、外部パートナーとの協働関係の強化、業務プロセスの標準化などに取り組んでいます。
財務安定性と収益性の両立
ディー・アップの経営基盤の強さは、財務安定性と高い収益性の両立にも表れています。売上高約57億円という規模でありながら、少数精鋭の組織体制と効率的な事業運営により、業界平均を上回る収益性を実現しています。
化粧品業界全体の動向を見ると、矢野経済研究所の調査によると、2023年度の国内化粧品市場は前年度比4.6%増の2兆4,780億円となり、堅調な成長を続けています。この市場成長の中で、同社は独自のポジショニングにより安定した成長を維持しています。
特に、アイメイク特化戦略による高い専門性と、垂直統合モデルによる効率的な事業運営が、安定した収益基盤の構築に寄与しています。自社での製造・販売により中間マージンを削減し、より高い利益率を確保できる体制を構築しています。
また、複数ブランドの展開と多チャネル販売により、特定の製品や販路への過度な依存を避け、リスク分散を図っています。これにより、市場環境の変化や競争激化に対する耐性を高め、持続可能な成長基盤を構築しています。
財務面での健全性は、新商品開発への投資余力や市場拡大への積極的な取り組みを可能にし、長期的な競争優位性の維持に重要な役割を果たしています。
人材育成と組織文化の構築
持続可能な成長を実現するためには、優秀な人材の確保と育成が不可欠です。ディー・アップでは、品質へのこだわりと顧客中心の価値観を軸とした組織文化の構築に注力しています。
従業員からの評価を見ると、「品質の高い商品を取り扱っているので、自社商品に自信が持てる」「商品の中身やクリエイティブにとことんこだわる姿勢は強み」といった声が聞かれ、製品品質への強いプライドと職業意識が醸成されていることが分かります。
人材育成においては、化粧品業界の専門知識と営業スキルの両方を身につけることができる実践的な研修体系を構築しています。特に、店舗提案型営業を行うためには、商品知識、売場づくりのノウハウ、コミュニケーション能力など多様なスキルが必要であり、これらを体系的に習得できる環境を提供しています。
また、少数精鋭組織の特性を活かし、若手従業員にも責任ある業務を任せ、早期からの実践経験を通じた成長機会を提供しています。これにより、個人の能力向上と企業の競争力強化を同時に実現しています。
組織文化の面では、「顧客第一」「品質重視」「スピード」「チャレンジ精神」といった価値観を共有し、全従業員が同じ方向性を向いて業務に取り組める環境づくりに注力しています。この強固な組織文化が、企業の持続的成長を支える重要な基盤となっています。
まとめ:ディー・アップの成功要因と今後の展望
株式会社ディー・アップのビジネスモデルと成長戦略を詳細に分析した結果、同社の競争優位性は以下の要因に集約されます。
第一に、アイメイク特化戦略による専門性の確立です。総合化粧品メーカーが多い業界において、アイメイクに特化することで独自のポジションを確立し、限られた経営資源を効率的に活用しています。特に「オリシキ」シリーズに代表される独自技術開発により、単なる価格競争から脱却した付加価値の高いビジネスモデルを構築しています。
第二に、垂直統合モデルによる効率性と品質管理の両立です。企画から製造、販売まで一貫した社内体制により、スピーディな商品開発と厳格な品質管理を実現し、市場変化への迅速な対応を可能にしています。
第三に、多チャネル展開と現場密着型営業による市場浸透力です。店舗提案型営業により小売店との強固なパートナーシップを構築し、同時にEC市場の成長機会も積極的に取り込んでいます。
第四に、少数精鋭組織による機動性と高い生産性です。約66名の従業員で売上高57億円を実現する高効率な組織運営により、意思決定の迅速化と個人の能力最大化を両立しています。
今後の市場展望としては、マスク着用の定着化によるアイメイク需要の継続的拡大、EC市場の更なる成長、消費者ニーズの多様化といったトレンドが予想されます。同社はこれらの市場機会を活かし、技術革新と顧客価値の創造を通じて、持続的な成長を実現していくことが期待されます。
美容業界を志望する就活生にとって、ディー・アップは「専門性」「技術力」「顧客密着」「効率経営」という現代企業に求められる要素を兼ね備えた注目すべき企業といえるでしょう。
